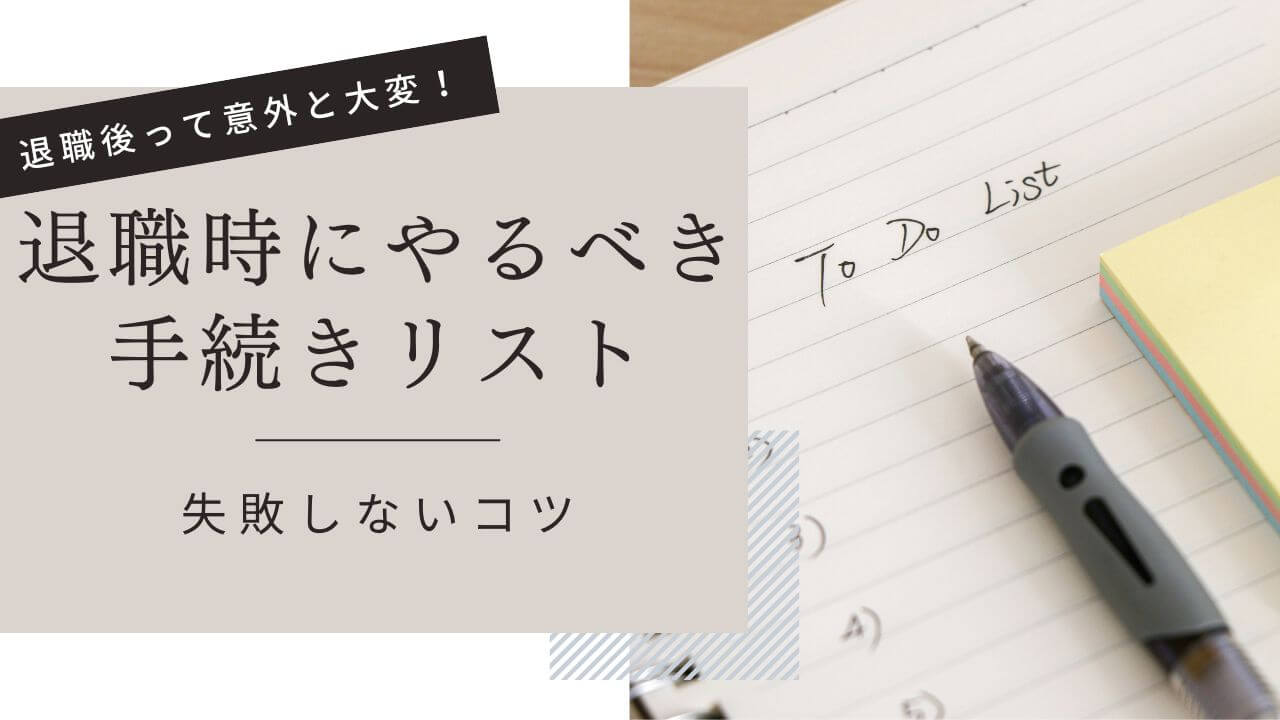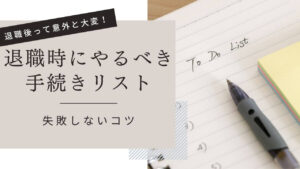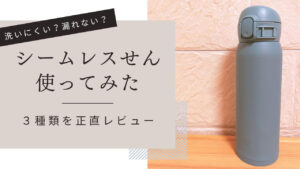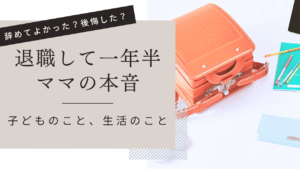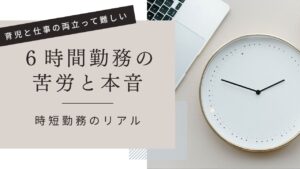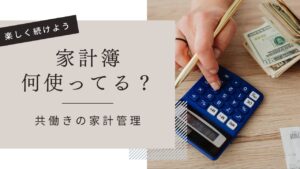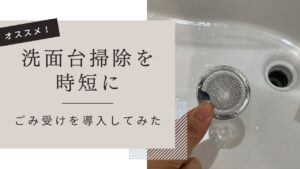こんにちは、yumeです。
昨年、20年間勤めた会社を退職しました。
その後待っていたのは、思った以上に大変な数々の手続き…。保険や年金などの処理に追われ、正直「もっと早く知っておけばよかった」と何度も思いました。
もし、あなたが退職を検討しているなら、こんな不安はありませんか?
- 退職後の手続きって何をやるのかわからない…。
- 何から始めたらいいのか不安でいっぱい。
- 手続きに失敗して損をするのが心配。
この記事では、私の退職経験をもとに、退職後に必要な手続きの流れを具体的に解説します。さらに、私がつまずいた失敗談もシェアします!
これを読めば、退職後の手続きで損をする心配がなくなり、不安が解消されるはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。

退職後の手続きリスト
退職時に行う手続きは以下のとおりです。会社や個人の状況によっては該当しない場合もありますので、手続きの要否について予め会社に確認しておくと安心です。
- 健康保険・国民健康保険の加入
- 国民年金への切り替え
- 企業型確定拠出年金(DC)の移換
- 企業年金の脱退一時金受け取り
- 失業手当の申請
- 保育園等利用の認定変更
- 住民税の納付
- 財形貯蓄の解約
- 通勤定期券の解約
- 労働組合からの脱退
健康保険・国民健康保険の加入
保険証は速やかに返却
退職後はそれまで使っていた保険証は使えません。速やかに会社へ返却します。
もし退職後に保険証を使用してしまったら、後日健康保険組合から返還請求が来て、健保が負担した分の医療費を支払うことになります。
退職後の健康保険はどうなる?
退職後に再就職しない場合は以下3つのいずれかを選択します。
- 退職前の健康保険を継続する
- 配偶者の扶養に入る
- 国民健康保険に加入する
私の場合は②で、夫の扶養に入っています。が、一度失敗しました。詳しくは後ほど。
①退職前の健康保険を継続する(任意継続保険)
退職してから20日以内に会社へ申請することで、退職前の健康保険に最長2年間加入を続けることができます。
任意継続保険の場合、同じ健康保険でも在職中と違う点があるので注意が必要です。
- 保険料は全額自己負担になります(在職中は会社とほぼ折半)
- 傷病手当や出産手当金はありません(在職中から継続している場合を除く)
保険料が高いし、手当金もないし…入るメリットがないのでは?と思いますよね。専業主婦になるなら全然メリットはありません。笑
以下のような場合は任意継続保険を選択するメリットがあります。
- 扶養家族がいる
- 国民健康保険にすると扶養家族も個別に加入するため、世帯全体としての保険料が高くなります。そのため、任意継続保険のほうが保険料において有利になる場合があります。
- 健康保険の福利厚生を利用したい
- 保養所や独自のサービスなどを利用することができます。
- 高収入である
- 健康保険では保険料の算定根拠となる報酬に上限があるため、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があります。
退職後20日以内に申請書を会社に提出し、保険料を支払います。
②配偶者の扶養に入る
配偶者が会社の健康保険に加入している場合、被扶養者として認定を受けることで保険料を負担せずに健康保険に加入できます。
以下2つの条件を満たしていれば、配偶者の被扶養者になることができます。
- 年間収入が130万円未満であること
- 収入が扶養者の収入の半分未満であること
被扶養者の年間収入は、「その年の1月〜12月の収入」という意味ではないのでご注意を!
- 過去の収入のことではなく、現時点から1年間の見込み収入額のこと
- 「収入」には雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるので注意
- 雇用保険の待機期間中でも収入要件を満たしていれば被扶養者として認定されます
- 基本手当の支給が始まったら扶養削除の届出が必要です
被扶養者になるための手続きは配偶者経由で実施します。
- 被扶養者(異動)届
- 扶養事実の申立書
- 生計維持関係を証する書類(所得証明書、住民票謄本、戸籍謄本など)
- 審査の結果、被扶養者として認定されると保険証が発行されます
被扶養者申請から保険証受領までは、3週間近くかかりました。
③国民健康保険に加入する
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない人(および生活保護を受けていない人)が加入する保険です。各市町村で運営されています。
以下の方が対象になります。
- 自営業
- 農業
- 年金生活者
- 無職
- 健康保険の扶養から外れた人
国民健康保険への加入手続きは、市区町村の窓口で行います。以下の書類を忘れずに持参しましょう。
- 健康保険資格喪失証明書(退職時に発行されます)
- マイナンバーカード(もしくは免許証、パスポート等)
- 銀行のキャッシュカードまたは通帳と届出印
- 保険料支払の口座振替手続きに使用します(別途WEBからも申し込み可能)
- 保険料の口座振替に対応している銀行を事前に確認しておくと安心です
保険証が発行されるまでは数日かかりますが、加入手続きの際に仮の保険証が渡されるので安心して医療を受けられます。
私の失敗談:夫の扶養に入れることに気づかず国保に加入
被扶養者の収入の考え方を勘違いして大失敗しました…。
被扶養者の認定条件にある「年間収入」を今年1年間の収入と思い込み、詳しく調べもせず国民健康保険の加入申し込みに行ってしまいました。
退職から1ヶ月ほど経過した頃に、偶然ネット記事で「健康保険の扶養、今年1年の収入と勘違いして損しちゃってる人が多いんですよね」といった記述を見て、この失敗に気づきました。
え?違うの?と詳しく調べてみると、前述したとおり今年1年ではなく、現時点から1年間の収入見込みでした。
私は専業主婦なので、今後1年間の収入はありません。扶養に入る条件を満たしていたのです。
夫に状況を話し、すぐ申請手続きに入りました。
手続きの流れはこちら
5月上旬にこの事実に気づき、夫(被保険者)から会社へ必要書類を送付してもらいました。
審査の結果、被扶養者として認定され、5月末ごろに保険証が届きました。
健康保険に加入すると、国民健康保険からは脱退する必要があります。これは自動では行われないため、自分で窓口へ行って手続きをしました。(オンラインでも可能です)
健康保険の保険証を提示し、国民健康保険の保険証を返却して終了。手続きはあっという間でした。
国保の保険証を利用していた場合どうなる?
ここで一つ問題が発生しました。
健康保険の保険証が届く前に、私は国民健康保険を使って医療機関を受診してしまっていたのです。
5月に被扶養者として認定されたため、4月利用分は国民健康保険ですが、5月分は健康保険を利用することになります。
国民健康保険脱退の際に、5月中に病院に行ったことを職員の方に話すと、医療機関から5月分の請求が国保にいってしまうので、健保に変える必要があると言われました。
同月内であれば医療機関へ保険証を見せるだけでOK
国保脱退の手続きに行った日はまだギリギリ5月。
「今から医療機関に行って、新しい保険証を見せてくれば間に合います」と言われ、そのまま病院や調剤薬局へダッシュ!それぞれの受付で健康保険に変わったことを話し、新しい保険証を提示。なんとか事なきを得ました。保険証を見せるだけで、複雑な手続きは何もありませんでした。
もし翌月になってしまったら
これが翌月になってしまうと、少々ややこしくなるみたいです。5月分は医療機関から国保へ請求されてしまうので、後日自分のところへ国保が負担した分の返還請求が来るそうです。それを払った上で、今度は自分で健康保険側へ請求をするのだとか。
聞くだけで大変そうだし、時間もかかりそう…。ギリギリ間に合ってよかったです。
保険料の納付
国民健康保険料の請求は6月ごろに来ます。口座振替または納付書によって納付します。
5月から健康保険に加入したので、4月分は国民健康保険の保険料を納めなければなりません。とても悔しい思いをしながら1ヶ月分の保険料を納めました。
国保の保険料、高かったです。もっと早く気づいていれば…。
5月分以降は健保の扶養に入っているので保険料の請求はありません。
一言アドバイス:まずは扶養から考えよう
専業主婦になる、もしくはパート等でこれから働く予定の人は扶養に入れるかどうか確認しましょう。国保にいきなり行っちゃだめです。保険料も高いです。
国民年金への切り替え
退職後は国民年金へ切り替え
転職で離職期間がない場合は次の会社で厚生年金が継続されますが、再就職の予定がない場合や離職期間がある場合は国民年金への切り替えが必要です。
国民年金のどの区分になるかは、健康保険や国民健康保険とセットで考えます。
国民健康保険または任意継続保険に加入する場合:第1号被保険者
国民健康保険に加入する場合は、国民年金の第1号被保険者への手続きも行います。保険と年金の窓口は市区町村の役所にありますので、合わせて実施してしまいましょう。
会社員の場合、在職中は健康保険と厚生年金に加入しています。退職後、健康保険は任意継続保険がありますが、厚生年金には任意継続の制度はありません。よって任意継続保険に加入する場合も国民年金に切り替える必要があります。
手続き方法
退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で加入申請書に必要事項を記入し、提出します。
必要書類
- 退職証明書や離職票など(退職日がわかるもの)
- 年金手帳
- 本人確認書類
健康保険の被扶養者になる場合:第3号被保険者
健康保険の扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者になります。年金保険料の負担はありません。
手続き方法
健康保険の被扶養者認定とあわせて、国民年金第3号被保険者の申請を行います。必要書類を会社に提出すれば完了です。
必要書類
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 年金手帳の写し
企業型確定拠出年金(企業型DC)の移換
退職前に企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた場合、退職から6ヶ月以内に個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換する必要があります。
移換しないとどうなる?
これまで積み立て、運用してきた資産は売却・現金化され、国民年金基金連合会の仮預かり口座へ移換されます。そうなると、資産は運用されず、管理手数料だけが毎月引かれていってしまいます。
せっかく増やしてきた資産が減ってしまう…!!
移換手続き
iDeCoを扱っている金融機関で手続きをすることになります。証券会社、銀行、保険会社などがあります。
私は楽天証券にしました。
もともと楽天証券でNISAをやっていたこともあり、手数料が安く投資商品ラインナップにも問題がなかったのでiDeCoも楽天証券で始めることにしました。
iDeCo開設はWebから申し込みができる
楽天証券であればWebで手続きができます。楽天証券HPからiDeCoのページを開き、案内に従って必要事項を入力するのみです。
申し込みから移換完了まではおよそ1ヶ月ぐらいでした。運用状況は楽天証券にログインすれば確認できるようになりますが、移換だからなのか、表示できるようになるまでは数週間かかりました。
投資先はリセットされる
企業DCからiDeCoへ移換すると、これまで企業DCで運用してきた資産は一旦現金化され、iDeCo口座に入金されます。それから改めてiDeCoで運用する商品を選び、購入していくことになります。
どの金融機関で開設するかによって、購入できる投資商品が違うので事前に調べておくと良いです。
楽天証券の場合、人気のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)をiDeCoで購入することができません。NISAや特定口座では購入できるのですが、iDeCoの対象商品には含まれていません。
その代わり、同じS&P500や全世界インデックスファンドである楽天・プラス・S&P500インデックスファンドや楽天・プラス・オールカントリー株式インデックスファンドを購入することができます。信託報酬も低く、NISAでも人気があります。
もしiDeCoでeMAXIS Slimシリーズを購入したい場合は、SBI証券やマネックス証券などで取り扱いがあります。
掛金を拠出する?orしない?
iDeCoの場合、毎月掛金を拠出して運用するか、拠出せず運用指図だけするかを選ぶことができます。しかし、運用に毎月手数料がかかるので、最低金額(5000円)で掛金を拠出し続けるほうが手数料以上の利益が期待できるかなと思っています。そのうちまた働くようになれば、掛金分は所得から控除できるので節税になりますし。
企業年金の脱退または移換
脱退一時金を受け取る
企業型DCの他に企業年金(確定給付企業年金)がある場合は、これまで積み立てられてきた年金原資を脱退一時金として受け取ることになります。企業年金からは脱退となるため、将来、企業年金分の年金受給はありません。
他の年金制度へ移換も可能
転職の場合、制度によっては転職先の企業年金へ移換することも可能です。移換して企業年金への加入を継続することで、最終的に年金として受け取ることができます。
また、個人型確定拠出年金(iDeCo)にも移換が可能です。
私の場合:移換せず一時金で受け取り、NISAへ
iDeCoへの移換も考えましたが、結論、一時金として受け取りました。
受け取り後はNISAで運用しています。必要なときに現金化できたり、投資商品の選択肢が多いというメリットがあります。また出口戦略が難しいと言われるiDeCoと比べると、受け取りも簡単です。
失業手当の申請
受給資格
原則として、離職日以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間があることが条件となります。ただし、以下に該当する場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば受給可能です。
- 倒産・解雇等による離職
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかった
- その他やむを得ない理由による離職
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等
- 妊娠、出産、育児等(受給期間延長の措置を受けていること)
- 家庭の事情の急変
- 通勤不可能または困難
- 企業の人員整理等による希望退職
注意!求職活動をしない場合は受給不可
失業手当は「失業した方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付」なので、求職活動をしない以下の人には支給されません。
- 家事または学業に専念する
- 家業に従事し、職業に就くことができない
- 自営を開始、または自営準備に専念する(※)
- 次の就職が決まっている
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望している
- 自分の名義で事業を営んでいる
- 会社の役員等に就任している
- 就職・就労中である(試用期間を含む)
- パート、アルバイト中である(※)
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再度就職の予定がある
※状況によっては受給可能な場合があります。ハローワークで確認しましょう。
私は専業主婦になったので、失業手当は受給していません。
受給方法
退職後、自分の住所を管轄するハローワークに必要書類を持参し、求職の申し込みをします。ハローワークにて、受給資格の確認・決定が行われます。
必要書類
- 離職票
- マイナンバーカード(持っていない場合は、マイナンバー確認書類および身元確認書類を持参)
- 写真2枚(縦3cm、横2.4cm)マイナンバーカードがあれば省略可
- 本人名義の預金通帳、キャッシュカード(ネット銀行、外資系金融機関は不可)
定期的な失業認定が必要
認定日(原則として4週間に1回)ごとに受給資格者証と失業認定申告書をハローワークへ提出する必要があります。ハローワークにて、就労の有無、求職活動の実績などが確認され、失業の認定が行われます。
待機期間と給付制限に注意
申請してもすぐに失業手当が給付されるわけではありません。待機期間が経過してから支給されますが、条件によってはさらに給付制限があります。
待機期間
受給資格が決定してから、失業状態が通算7日間経過するまでの期間のこと。この間の失業手当は支給されません。
給付制限
自己都合で退職した場合、待機期間満了の翌日からさらに2ヶ月または3ヶ月間、失業手当の給付が行われません。
保育園等の利用認定の変更
前月までに変更手続きが必要
会社を退職する場合は、保育園や幼稚園の預かり保育の利用認定を変更する必要があります。
変更を必要とする月の前月までに、市区町村の窓口にて認定変更申請書を記入し提出します。利用中の施設(保育園、幼稚園等)では特に手続き等はありません。
「求職中」へステータス変更
退職すると「求職中」の状態に変更することになります。
求職中の場合、3ヶ月間保育施設の利用資格が継続されます。その間、新たに就職が決まれば、就労証明書を提出することで継続して保育施設を利用できるようになります。
認定の取り消しになると思っていたので「求職中」への変更は正直予想外でした。
退職後3ヶ月間は預かり保育を利用できる状態にはなりましたが、私の場合は不要だったので利用しませんでした。
3ヶ月経過すると有効期間満了
認定変更から3ヶ月を過ぎると有効期間満了となり、保育施設の利用は終了となります。(事前に「有効期間満了のお知らせ」が自治体から届きます。)
その後、就職等により改めて保育園等の利用が必要になった場合は、また初めから手続きを行い認定を受けることになります。
住民税の納付
納付方法は3種類
退職時に住民税を納付する方法は3種類あります。退職する時期によって選択できる納付方法が異なります。
- 一括徴収
- 最終給与や退職金から一括で徴収される
- 普通徴収
- 自治体から送付される納付書を使い、自身で納付する
- 特別徴収
- 再就職する場合、勤務先の給与から天引きされる
1月〜5月に退職
原則として一括徴収となります。退職月までは給与から天引きされ、退職後から5月分までが一括で徴収されます。
6月〜12月に退職
原則として普通徴収となりますが、一括徴収も選択可能です。
転職が決まっている場合
転職先で特別徴収を継続することが可能です。
住民税の支払いはこれで終わりではない
私は3月退職だったので、4月〜5月分は退職金からの一括徴収となりました。
ですが、住民税の支払いはそれで終了ではありません。
今まで払っていたのは前年度分の住民税。今年度分の納税通知は6月から7月頃にやってきます。納税額は前年の所得によって算出されるため、懐にガツンとくる大きな金額になります。
財形貯蓄の解約
財形貯蓄を契約している場合は、解約等の手続きが必要になります。
退職後の選択肢は3つ
退職すると財形貯蓄の積立は継続できません。以下のいずれかを選択します。
- 解約
- 再就職先で継続
- 退職時の手続きは不要。再就職先で継続手続きを行う。
- 金融機関に据え置き(最長2年間、積立は不可)
- 退職時の手続きは不要。
解約手続き
解約する場合は、退職日までに解約申込書を会社に提出します。提出から1ヶ月〜1ヶ月半程度で指定した口座へ残高が振り込まれます。
私の失敗談:期限に間に合わず、時間とお金を無駄遣い
解約申込書の提出期限に間に合わず、銀行窓口で解約手続きをすることになりました。
会社から手続きの案内が届いたのは退職日前日。大量の書類から財形貯蓄の解約方法を探し出したときにはすでに手遅れでした。仕方なく銀行窓口を訪れることに…。
銀行窓口では口座番号が必須
窓口では申込書だけでは手続きができず、別の用紙に記入し、口座を確認して解約という流れになりました。
ここで大きな失敗が一つ。財形貯蓄の口座番号を全く把握していなかったのです。会社経由では記入の必要がなかったので意識していませんでしたが、窓口では必須でした。
定期的に送られてくる残高通知に記載されているので、これを持参すればスムーズでしたが、私は持っていなかったため、銀行の方が確認作業をしてくれるまで長時間待つことになりました。
解約後、数日で入金されたので結果的には会社経由より早かったのですが、窓口での手続き時間や交通費が無駄でした。
一言アドバイス:解約手続きは退職前に済ませよう
私は会社からの案内があるまで財形貯蓄について全く考えていませんでした。退職後に手続きするものだと思い込んでいたのが原因です。
通勤定期券の解約
退職後、通勤費のうち退職日以降の分は返納する必要があります。
定期券は解約のタイミングによって払い戻し額が大きく変わります。損をしてしまわないよう、退職後は速やかに払い戻し手続きを行いましょう。
私の失敗談:たった数日で1ヶ月分の損失!
退職後、私は定期券を数日放置していました。
解約しようとしたら、ちょうど払い戻し額が減る日を過ぎたばかり…!!
退職した時点で3ヶ月分残っていた定期券をさらに1ヶ月使用したことになってしまいました。会社には3ヶ月分返納しましたが、払い戻されたのは2ヶ月分。1ヶ月分の損失は本当に痛かったです。
もう少し早く解約していれば…。
一言アドバイス:退職したら即解約!
数日ぐらい大丈夫…なんて思ってはいけません。退職したら速やかに払い戻し手続きをしましょう。
労働組合からの脱退
退職時には、労働組合からの脱退手続きも忘れずに行いましょう。
退職後も自動的に脱退にはならない
労働組合からの脱退は自分で手続きをする必要があります。会社から案内されることもないため、自ら組合に連絡し脱退の意思を伝えましょう。
労働組合の脱退は盲点になりやすい
会社から来る案内には労働組合のことは全く触れられていません。会社とは別組織なので当然といえば当然ですが…。そのため、脱退が必要であるということに気付きにくいです。
私自身、退職後もしばらく組合の広報誌が自宅に届き続けたことから、まだ加入状態であることに気付きました。このままでは組合費の請求が来てしまうと焦り、すぐ組合に連絡し手続きを行いました。
無事に脱退できて安心しましたが、早く気づかなければ損をするところでした。
一言アドバイス:退職時に脱退を確認しよう
労働組合の脱退は忘れがちですが、放置すると余計な出費やトラブルの原因になります。退職前に必ず確認し、スムーズに手続きを済ませておきましょう!
まとめ
退職時には短期間で多くの手続きが必要になります。慌てて手続きを誤ってしまったり、忘れてしまったりすることの無いよう、事前にしっかり準備をしておきましょう。
会社に期待してはダメ
実際に退職してわかったことですが、正直なところ、会社は辞める人間にはそれほど親切ではありません。
手続きの案内はしてくれますが、退職日直前であったり、書類が難解であったり、会社任せにしていると苦労します。
早めに自分で情報収集
退職を決めたら、手続きに関する情報収集を早めに行いましょう。疑問点などがあれば、早い段階で解決しておくと安心です。
気持ちよく新たな生活をスタートしよう
事前の情報収集や準備、手続きのスケジューリングを行うことで、退職後も慌てることなく手続きを進めることができます。
自ら早めに行動し、気持ちよく新生活をスタートしましょう。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。